
2025年6月版 カーボンニュートラル取り組みまとめ
最近よく耳にするようになった「カーボンニュートラル」「脱炭素」「ネットゼロ」という言葉。「なんかよくわかんないけど、環境問題対策でしょ?」はい、そのとおりです。
私たちの住む日本でも、地球温暖化や異常気象などの課題に本格的に向き合い、さまざまなレベルで取り組みが進んでいます。本記事では、国・自治体・企業それぞれの最新の動きと、私たち一人ひとりができること、特にカーボンニュートラルについて解説していきます。
もくじ
1. 日本のカーボンニュートラルとは?
「カーボンニュートラル」とは、ザックリ言うと
私たちの生活から排出された二酸化炭素(カーボン)を、植物に吸収させて「行って来いでチャラ」(ニュートラル)にすること。
理科で習いましたね?植物は、太陽光などの光エネルギーをつかって、二酸化炭素と水を原料に、様々な栄養分と酸素を作ります。
私たちの生活で排出された二酸化炭素を、植物にどんどん吸収してもらって、減らしていきましょう!ということです。
ただ、植物を増やせばいいのかというと、それだけではありません。
植林などができる土地も限られているので、私たちの生活から排出される二酸化炭素量を減らすことも必要です。
環境省によるカーボンニュートラルの定義は下記のリンクをご参照ください。
https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/about/
日本政府は2020年10月、2013年度を基準年として「2050年までにカーボンニュートラルを実現する」と宣言しました。その前段階として「2030年までに温室効果ガスの排出を46%削減する」ことを目標にしています。
これからの季節よく聞くようになるかと思いますが「猛暑」など地球温暖化による深刻な影響を少しでも抑えるため、世界各国と足並みをそろえ、日本としても早期から脱炭素社会を目指す決意を表したものです。
ちなみに、2030年目標まであと5年ですね。どこまで削減出来ているのでしょうか?
日本国温室効果ガスインベントリ報告書2024年*1によりますと、2013年の排出量14億800万トンに対し、2022年時点で11億3,500万t(いずれも二酸化炭素(CO2)換算)になっているそうです。
2030年目標は、約7億6,000万t…全然行けそうな雰囲気が無いですけども、諦めずに、でも無理もせず、みんなで目標達成に向けてがんばっていきましょう!
*1 日本国温室効果ガスインベントリ報告書URL:
https://www.env.go.jp/content/000226851.pdf
2. 政府の方針と主な施策
日本政府は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて「グリーン成長戦略」を柱とした政策を展開しています。これは、環境対策と経済成長を両立させることを目的に、14の重点分野(再エネ、EV、蓄電池、洋上風力、水素など)を定め、企業や自治体の取り組みを後押しする内容です。

代表的なものは、下記の4項目。
- 再生可能エネルギーの導入促進(太陽光・風力など)
- 電気自動車(EV)や燃料電池車の普及支援
- 省エネ機器の導入補助金制度
- 企業への脱炭素経営の支援
その中でも特に注目されているのは「再生可能エネルギーの普及加速」と「電動車の普及」です。住宅や工場への太陽光パネル導入支援、再エネ電力の導入補助、そして電気自動車購入時の補助金制度などが用意されています。
また、企業向けには脱炭素設備への投資支援や税制優遇があり、GX(グリーントランスフォーメーション)リーグなどを通じて脱炭素経営を促進しています。
さらに、2023年には「GX実行会議」が立ち上げられ、炭素に価格をつける仕組み(カーボンプライシング)の導入なども議論されています。これにより、二酸化炭素排出量を減らす行動にインセンティブが生まれ、民間の投資を呼び込むことが期待されています。
3. 自治体の取り組み
日本全国の自治体でも、地域性に応じたカーボンニュートラルの取り組みが広がっています。東京都は「ゼロエミッション東京戦略」*2を掲げ、2030年までに温室効果ガス排出量を半減することを目指しています。新築住宅への太陽光パネル設置義務化やEV充電インフラの整備など、生活に密着した対策が特徴です。
また、地方都市でも独自の施策が進行中です。たとえば長野県飯田市では、市民参加型で再エネを地産地消する「地域電力会社(おひさま進歩エネルギー)」*3が運営されており、地域経済の活性化と脱炭素の両立を実現しています。福岡県北九州市では、水素エネルギーの活用に先進的に取り組み、公共バスや発電への利用*4が始まっています。
さらに、国が認定する「脱炭素先行地域」制度により、先進的な自治体には重点的な支援が行われています。これにより、地域間での取り組みの広がりとモデルケースの創出が進んでいます。
*2 ゼロエミッション東京戦略 Beyond カーボンハーフ URL:https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/policy_others/zeroemission_tokyo/strategy_beyond_carbonhalf
*3 おひさま進歩エネルギー株式会社 URL:
https://ohisama-energy.co.jp/
*4 北九州水素タウン構想 URL:
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000759331.pdf
4. 企業の主な取り組み傾向
企業も「カーボンニュートラル」が無視できない時代に入っています。
特に製造業では、二酸化炭素排出量の多い生産工程の見直しが進み、パナソニックやトヨタなどは、再エネ由来の電力を使った「グリーン工場」への転換を加速しています。自動車業界では、EVや水素自動車の開発が本格化しており、2050年を見据えた脱ガソリン化の動きが世界的に広がっています。
一方、IT業界では、データセンターが消費する電力の再エネ化(太陽光発電など)が注目されており、富士通やNTTは再生可能エネルギー100%による運営を目指す取り組みを展開中です。また、リモートワークやクラウド化により、オフィスや出張の削減による間接的な排出削減も進んでいます。
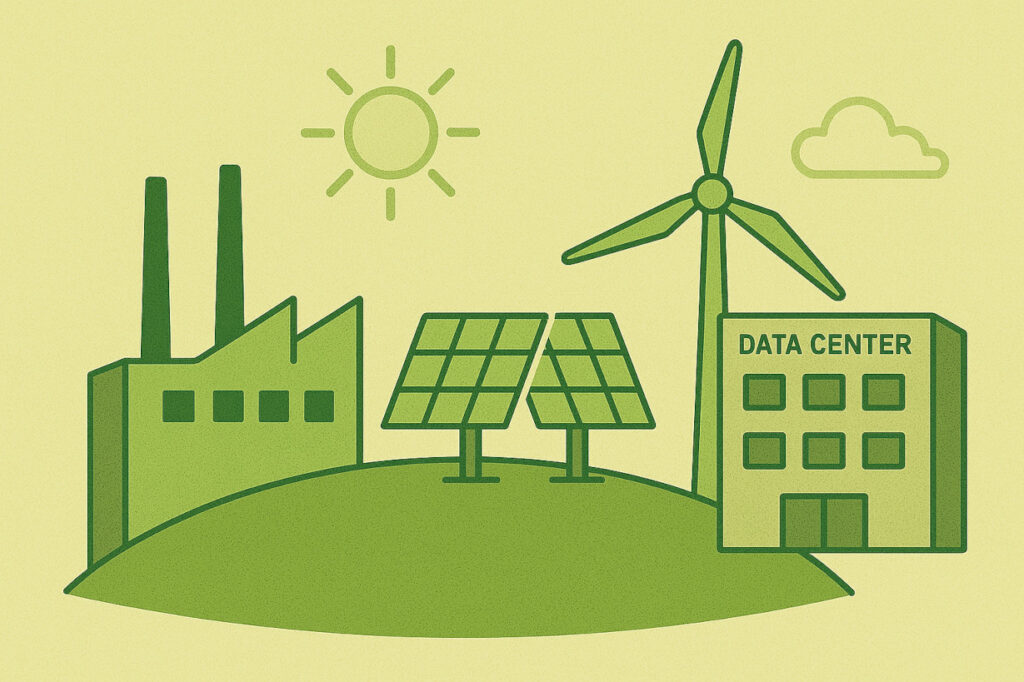
最近では「ESG投資」や「サステナビリティ報告書」が企業評価の指標にもなってきており、取引先や消費者に対する透明性や、環境問題に対する姿勢が重視されるようになっています。大手から中小企業まで、脱炭素経営が新たなスタンダードになりつつあります。
5. 私たち一人ひとりの役割と支援制度
カーボンニュートラルの実現には、政府や企業だけでなく、私たち一人ひとりの行動もとても大切です。家庭でのエネルギー消費は、日本全体の約15%を占める*5とされており、省エネ家電の使用、照明のこまめな消灯、冷暖房の温度設定の見直しなど、身近な工夫で二酸化炭素削減に貢献できます。また、徒歩や自転車、公共交通機関の利用も立派な脱炭素アクションです。

私たちにできることの例
- 節電や節水を意識する
- 省エネ家電に買い替える
- 電気を再エネに切り替える(電力会社の再エネプランを選択するなど)
また、政府や自治体は次のような支援制度を用意しています。
- 省エネ家電購入への補助金
- 太陽光発電や定置型蓄電池・EVの導入支援
- エコカー減税や購入補助金
最近では「環境ポイント制度」や「カーボンマイレージ」といった、環境配慮の行動に応じてポイントが貯まる取り組みも始まっています。楽しみながら参加できる制度が広がることで、脱炭素がより身近なものになりつつあります。
*5 資源エネルギー庁 エネルギー白書2022 第2節 URL:https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2022/html/2-1-2.html
6. 今後の注目トピック
カーボンニュートラルの流れが加速する中で、今後特に注目すべきトピックがいくつかあります。
- 再エネ導入のさらなる加速
地域での太陽光や風力発電の普及、電力会社の再エネ比率アップなど。 - CBAM(炭素国境調整措置)への対応
生産過程で排出される二酸化炭素の多い製品に課税する仕組み。 - グリーンファイナンスの活用
脱炭素に取り組む企業に対し、銀行や投資家が優遇融資や資金提供を行う動き。
「二酸化炭素いっぱい排出するから罰金!」とか、「二酸化炭素あんまり出さないからご褒美。」といったこれらのトピックは、日本だけでなく世界全体の流れとも密接に関係していて、今後の政策やビジネスの方向性を大きく左右していくものになりそうですね。
7. まとめ
カーボンニュートラルは、気候変動という地球規模の課題に対する、私たち全員のチャレンジです。日本は2050年の実現に向けて、明確な方針を打ち出し、自治体・企業・市民それぞれが役割を果たす形で動き出しています。再生可能エネルギーの普及、脱炭素製品やサービスの開発、省エネ行動の促進など、その取り組みは社会全体に広がっています。
また、最近では環境への配慮が企業の信頼やブランド力にもつながり、投資家や消費者からの評価にも直結するようになってきました。一方で、私たち一人ひとりの選択、たとえば、電力プランの見直しやエコ家電への買い替えなども、関係無いようで実は未来を左右する大切なアクションです。
このような動きが連鎖し、広がっていくことで、持続可能な社会が形になっていきます。難しく考えすぎず、「できることから少しずつ」始めることが、カーボンニュートラルへの第一歩です。未来の地球を守るために、私たち自身がその一員であることを意識しながら、無理せず我慢せず前向きに取り組んでいきましょう。
ベランダに植木鉢ひとつ置いて観葉植物などを育てるのも、ECサイトで購入したものをなるべくまとめて配送してもらうことも、立派なカーボンニュートラルへの取り組みだと思います。